安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会の機能を統合したものであり、
【労働者の安全と健康の確保】・【職場環境の質の向上】・【労働災害の防止】を目的に設置される組織です。一定規模以上の事業場では設置が義務付けられています。
1.安全衛生委員会に関する法体系の概要
労働安全衛生法 の第17~19条は委員会について明記されています。
第17条【安全委員会】について
第18条【衛生委員会】について
第19条【安全衛生委員会】について
より詳細版となる、労働安全衛生法施行令では第8~9条にあたります。
第8条【安全委員会を設けるべき事業場】
第9条【衛生委員会を設けるべき事業場】
さらに詳細版となる、労働安全衛生規則では第21~23条の2にあたります。
第21条【安全委員会の付議事項】
第22条【衛生委員会の付議事項】
第23条【委員会の会議】
第23条の2【関係労働者の意見の聴取】
2.安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業場
(労働安全衛生法施行令 第8条、9条)
常時50人以上であれば業種にかかわらず必ず衛生委員会は必要ですが、事業場の業種と人数によっては、安全委員会を作る義務はありません。自分事業場がどの業種になるか確認したい場合は、所轄の労働基準監督署へ問い合わせが必要です。
林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
では50人以上で安全委員会が必要です。
製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
では、100人以上で安全委員会が必要です。
3.安全衛生委員会の構成と開催頻度
(労働安全衛生法 第17条、18条,19条)
安全衛生委員会は、労働側と会社側の代表者で構成されます。
具体的には以下のメンバーとなります。人数に法的な定めはありません。
- 総括安全衛生管理者または事業者が指名した者を1名(委員長)
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 産業医
- 事業場の労働者で、衛生や安全に関し経験を有する労働者の代表
※委員の半数について
①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の推薦に基づき指名しなければなりません。
②過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者に基づき指名しなければなりません。
(労働安全衛生規則 第23条1項)
委員会は毎月1回以上開催することが義務付けられています。
(労働安全衛生規則 第23条3項)
議事の概要を掲示・メール・回覧するなどして労働者に周知させなければなりません。
(労働安全衛生規則 第23条4項)
委員会の議事録は3年間保管する必要があります。
4.安全衛生委員会での主な議題
(労働安全衛生法 第17条第1項、第18条第1項)
安全衛生委員会では、「調査審議」と呼ばれる事項について話し合いや確認を行います。
ここが一番の悩みどころです。年間でスケジュールを立てて漏れがないように行いましょう。
安全面(安全委員会)
労働安全衛生規則の第21、22条に難しく書かれていますが、
厚生労働省のHPには、以下のように記されています。
1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2. 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
3. 安全に関する規程の作成に関すること。
4. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
5. 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
6. 安全教育の実施計画の作成に関すること。
7. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
引用:安全委員会、衛生委員会について教えてください。
衛生面(衛生委員会)
同じく厚生労働省のHPには、以下のように記されています。
1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4. 衛生に関する規程の作成に関すること。
5. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
6. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
7. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
8. 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
9. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
10. 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
11. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
12. 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
13. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
14. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
引用:安全委員会、衛生委員会について教えてください。
委員会のスケジュール例
文章だと分かりにくいので、スケジュールにすると、以下のようなかんじです。
| 開催月 | 審議・確認事項 |
|---|---|
| 4月 | 新入社員・職長教育の実施、火災警報器の確認 |
| 5月 | 作業環境測定、特殊健康診断、火災・自然災害時の対応確認、消火器体験 |
| 6月 | 熱中症予防、救急箱チェック |
| 7月 | 安全衛生に関する社内アンケートの実施 |
| 8月 | 化学物質のリスクアセスメントの見直し |
| 9月 | 定期健康診断、ヒヤリハットの抽出、 |
| 10月 | リスクアセスメントの改定 |
| 11月 | 作業環境測定、特殊健康診断、リスクアセスメント結果の協議 |
| 12月 | ストレスチェック |
| 1月 | 安全衛生に関する社内アンケートの実施 |
| 2月 | 安全規定の見直し |
| 3月 | 来季のスケジュール作成 |
毎月:
労働者の残業時間の確認、社用車の安全点検記録の提出、清掃記録の提出、安全パトロール報告書の提出、保護具の確認
都度:
労災発生時は報告書を確認、法改正の連絡、産業医の面談、特別教育の報告
5.会議以外の具体的な活動内容
安全衛生委員会の活動は多岐にわたります。以下に主な活動内容を示します:
① 安全衛生計画の策定と実施
年間を通じての行動計画を作成します。この計画には、安全衛生方針、安全衛生目標、重点実施事項が含まれます。計画の内容としては、具体的な実施内容、実施時期、役割分担、費用などを記載します。
②ストレスチェックの実施と対策
ストレスチェックの実施計画を審議し、その実施状況や組織分析結果を報告します。結果に基づいて、職場環境の改善や個人へのケアなどの対策を検討します。
③長時間労働対策
長時間労働の状況を報告し、その対応について協議します。過重労働による健康障害を防止するための対策を立案し実施します。
④健康診断の実施と結果の活用
定期健康診断の実施状況や結果を報告し、共有します。結果に基づいて、必要な健康管理対策を検討し実施します。
⑤ 職場巡視とリスクアセスメント
定期的に職場を巡視し、危険箇所や改善が必要な点を把握します。また、リスクアセスメントを実施し、特定された危険有害要因に対する低減対策を検討します。
⑥労働災害の分析と再発防止
労働災害が発生した場合、その原因を分析し、再発防止策を検討します。また、ヒヤリハット事例の報告や分析も行い、潜在的なリスクの低減に努めます。
⑦安全衛生教育の計画と実施
労働者に対する安全衛生教育の実施計画を作成し、実施します。これには新入社員教育、職長教育、特別教育などが含まれます。
⑧作業環境測定と改善
作業環境測定の結果を評価し、必要な改善対策を立案・実施します。これには騒音、粉じん、有害物質などの管理が含まれます。
⑨メンタルヘルス対策
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策を検討し実施します。これには、メンタルヘルス研修の実施、相談窓口の設置、職場環境の改善などが含まれます。
⑩化学物質管理
職場で使用される化学物質の適正管理について検討し、必要な対策を実施します。これには、安全データシート(SDS)の管理、適切な保護具の選定・使用、作業手順の見直しなどが含まれます。
6.安全衛生委員会の効果的な運営
安全衛生委員会を効果的に運営するためには、以下の点に着目しましょう。
- 経営トップの関与:経営トップが安全衛生方針を明確に表明し、委員会活動に積極的に関与することが重要です。
- PDCAサイクルの実施:計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを回し、継続的な改善を図ります。
- 従業員の参加促進:従業員の意見を積極的に取り入れ、全員参加型の安全衛生活動を推進します。
- 情報の共有:委員会での議論や決定事項を従業員に適切に周知し、安全衛生意識の向上を図ります。
- 専門家の活用:産業医や外部の安全衛生コンサルタントなど、専門家の知見を積極的に活用します。
- 目標の設定と評価:具体的かつ測定可能な安全衛生目標を設定し、定期的に進捗を評価します。
- 最新情報の収集:法改正や新たな安全衛生技術など、最新の情報を常に収集し、活動に反映させます。
おわりに
安全衛生委員会は、労働者の安全と健康を守るための重要な組織です。
効果的な運営により、労働災害の防止、職場環境の改善、労働者の健康増進が図られ、結果として生産性の向上や企業価値の向上にもつながります。経営者、管理者、労働者が一体となって取り組むことで、より安全で健康的な職場づくりを実現していきましょう。
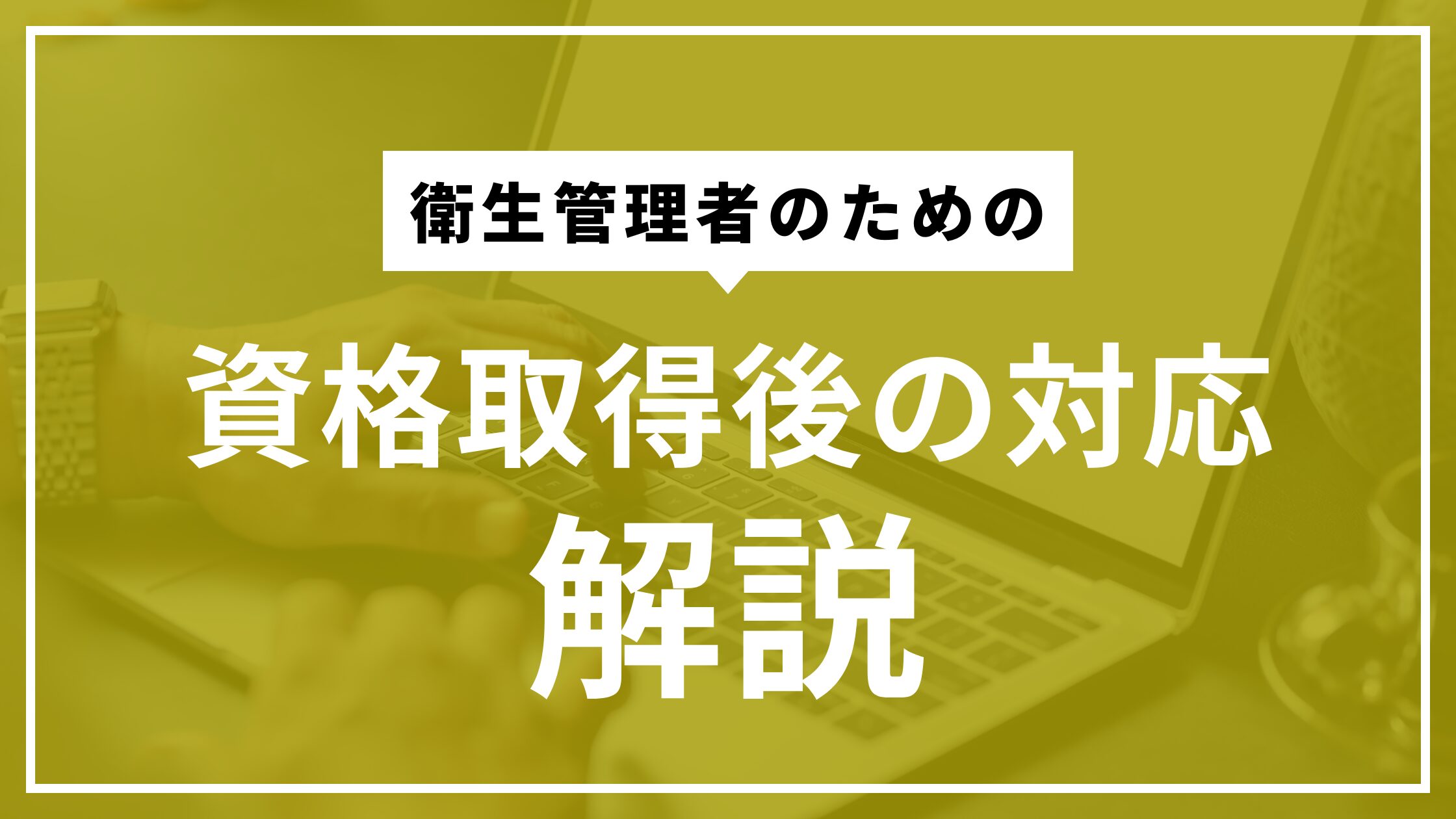
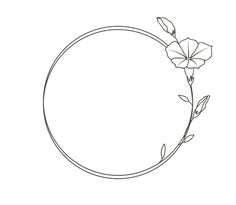

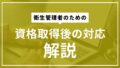
コメント