労働衛生管理体制を整えるのに設置が必要な「作業主任者」は、危険や有害な業務から労災を防止するために必要な資格です。作業主任者には「免許」と「技能講習」があり、それぞれ取得方法や役割、適用範囲が異なります。以下では、免許と技能講習の違いを解説します。
1.免許と技能講習の概要
免許となっている場合
【定義】: 国家試験に合格することで取得できる資格。
【難易度】: 特別教育や技能講習よりも難易度が高い。
【取得方法】: 労働安全衛生法に基づいた国家試験を受験し、合格する必要がある。
【学習期間】:数週間~
【適用範囲】: 高度な危険作業や専門性が求められる業務に必要。
例: 高圧室内作業主任者免許、ガス溶接作業主任者免許、特級ボイラー技士免許など。
試験は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会 にて受け付けられています。
技能講習となっている場合
【定義】: 登録された教習機関で講習を受け、修了試験に合格することで取得できる資格。
【難易度】: 免許よりは低いが、特別教育よりは高い。
【取得方法】: 指定された教習機関で講習を受けた後、修了試験に合格する。
【学習期間】:1~数日
【適用範囲】: 中程度の危険作業や作業指揮監督を行う場合に必要。
例: 石綿作業主任者技能講習、有機溶剤作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習など。
講習は、都道府県労働局長の登録を受けた機関にて行われています。
修了試験に合格しやすいようにか、大事なところは講習中に教えてくれました。試験は難しくないですが、危険業務に従事するための講習であるため、しっかりと講習を受けましょう。
※労働安全衛生法の危険有害業務(第59条3項)は、上記プラス「特別教育」の計3種類がありランク分けされています。特別教育は一番下で、例として「フォークリフト」があります。
2.責任範囲の違い
労働安全衛生法では、特定の危険有害な作業について「免許」または「技能講習」の修了が義務付けられています。どちらも作業主任者としての責任が伴います。無資格で作業を行わせた場合、事業者には50万円以下の罰金などの罰則があります。
免許の責任範囲
広範囲の指揮・監督を行うため、責任範囲は広く、高度な知識と技術が求められます。
国家資格であるため、公的な信頼性が高く、指揮監督を行うのに説得力があります。
技能講習の責任範囲
特定の危険作業の指揮・監督に従事するため、一定の専門知識が必要とされます。
まとめ
「免許」と「技能講習」は、それぞれ異なる目的と役割を持ちます。免許は高度な専門知識と技術力を証明する国家資格であり、高度な危険作業に必要です。一方で技能講習は比較的短期間で取得可能で、中程度の危険性を伴う作業や指揮監督に対応します。どちらも労働安全衛生法に基づき、安全な職場環境を確保するために欠かせない資格です。
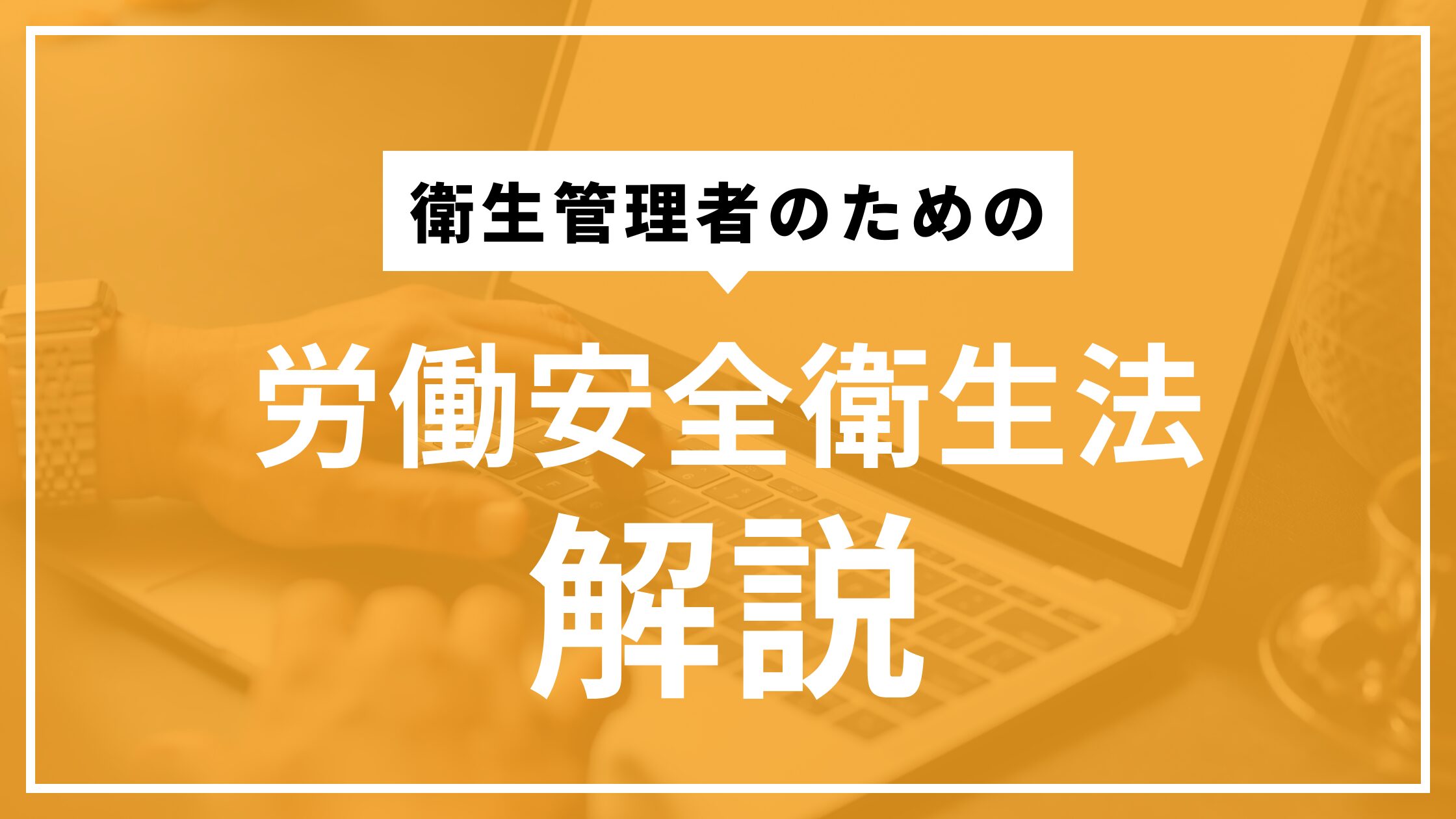
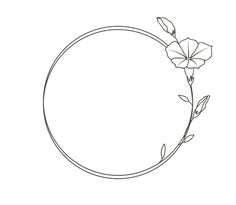
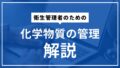

コメント